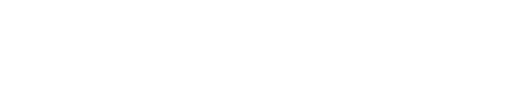開催終了・報告はこちら
メディアから東京を考え、東京からメディアを考える
日時 :2021年1月23日(土曜)午後4時から6時
方法 :オンライン開催
報告者:水出幸輝(京都大学特別研究員(PD))
松山秀明(関西大学)
応答者:難波功士(関西学院大学)
司 会:大尾侑子(桃山学院大学)
趣旨:
新型コロナウイルス感染拡大のいま、「東京」の都市イメージが揺らいでいる。2020年に開催されるはずだった東京オリンピックは延期され、テレビや新聞、インターネットでは連日のように東京の感染者数の増減を報道している。本来、メディアイベントの中心地となるはずだった2020年の首都は、逆に、感染拡大が危惧される地域となり、政治、経済の中心地としての「東京」の地域的特性はゆらぎつつある。
本研究会では、水出幸輝会員と松山秀明会員によるそれぞれの近著を出発点に、「メディアと東京」の関わりの歴史を振り返り、現在の東京が置かれている歴史的、社会的状況をメディア文化研究の視点から検討したい。
まず、水出幸輝会員の著書『〈災後〉の記憶史』(人文書院、2019年10月)では、東京を襲った関東大震災と地方を襲った伊勢湾台風を事例に、日本社会における災害認識の変遷を新聞報道から通時的に検討している。そこでは1960年の「防災の日」制定が関東大震災をナショナルな記憶に押し上げていくことが指摘され、これは1960年代以降のメディア編成が「東京=ナショナル」という認識をより強固にしていく様子を示している。
続いて、松山秀明会員の著書『テレビ越しの東京史』(青土社、2019年11月)では、1953年に誕生したテレビが、戦後日本社会の東京観をいかに規定してきたかを通時的に明らかにする。1964年の東京オリンピックを頂点として以降、テレビは番組としても産業としても制度としても、「東京」という首都のイメージに大きな役割を果たしてきた。これもまた、テレビというメディアによる東京の一極集中化の様相である。
以上の2つの歴史的な議論をもとに、討論者に難波功士会員を迎え、まず「メディアと東京」をめぐる過去を考えたい(出版年から分かるように、それぞれの著書はコロナ禍直前に書かれている)。そのうえで、2020年に起きた変化について考え、これからの「メディアと東京」のあり方を参加者とともに議論したい。
お申し込み・お問い合わせは佐伯順子まで、1月20日午後5時までメールでお願い申し上げます。