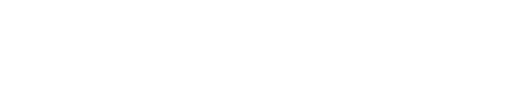■日 時: 2025年1月16日(木) 18:00~19:30
■場 所:オンライン(Zoom)
■報告者:Cherie Leung(Regulatory Policy Executive, CAP)
■討論者:小西美穂(関西学院大学)、藤田真文(法政大学)
■司 会:治部れんげ(東京科学大学)
■企画趣旨:
本研究会は、広告とジェンダー表現を巡る規範形成の過程の理解を深めることを目的としている。近年、ジェンダーステレオタイプを含む広告が消費者から批判される事象が後を絶たない。加えてSNS空間では広告に対する批判を日本国憲法21条が定める表現の自由への侵害と位置づける対抗言説が見られる。この現象は新制度派組織論(制度理論)でいう新たな制度形成の過程と位置付けることが可能であり、制度形成における正当化ロジックを分析することは一般化可能な示唆を得ることができる。
今回の研究会では、英国におけるジェンダーステレオタイプ広告規制について新たなルールを策定した非営利団体:広告実践審議会(以下、CAP)の規制責任者を招き、導入の背景や議論、その後の広告表現の変化などについて聞いた上で議論を行う。報告者選定の理由は以下の通りである。
2018年12月14日、英国においてCAPはジェンダーステレオタイプと広告に関する新しいルールを発表、2019年6月14日から導入した。CAPは広告標準化協会(ASA)と連動して活動する英国の広告、メディア企業が集まる団体であり、自主規制ルールなどを定めている。新しいルールにより、有害な(harmful)ジェンダーステレオタイプを含む広告やCMは英国のテレビなどでは流せなくなった。既に、フォルクスワーゲンやフィラデルフィア・クリームチーズなど大手メーカー製品でCM撤去事例がある。自主規制導入に先立つ2012年からASAでは有害な広告に関する議論が始まり、2016年からは、特にジェンダーステレオタイプを含む広告の害について議論が重ねられてきた。特に2015年に起きた水着女性の写真を使った広告炎上は議論に影響を与えたようである。
本研究会では、英国における広告発信者の業界団体から具体的な取り組みと効果や限界について聞くことで「ジェンダーステレオタイプ」の定義や日本と異なる文化圏における認識の比較、広告規制を巡る企業や広告制作者の視点を理解することを目的とする。本研究会は研究者やメディア実務家に加え学生の参加を歓迎する。限られた時間で有益な議論をするため、参加者は企画書脚注に示した基本資料に目を通すことをお勧めする。なお活発な議論を可能にするため日英通訳の手配を検討している。
【開催記録】
■記録作成者:治部れんげ
■参加者:69名(zoom、登壇者・通訳者を除く)
本研究会では、治部れんげからの趣旨説明の後、Cherie Leung氏より、英国の広告標準化協会(Advertising Standard Authority :ASA)と広告実践審議会(Committee of Advertising Practice : CAP)の役割、そして2018年に発表されたジェンダーに関する有害なステレオタイプを含む広告の規制について説明があった。続いて藤田真文氏、小西美穂氏より日本におけるテレビ番組やCMの実状やルールを踏まえたコメント、質問があった。その後、質疑応答を行った。
Leung氏の報告では、CAPが広告に関する規制について審議を行うこと、導入された規制に基づき消費者から寄せられた苦情に基づきASAが審査を行うことが示された。ジェンダーステレオタイプに関しては、見た人の「不快感」に基づく苦情が寄せられることもあるが、ASAの審査基準は感情のみではなくエビデンスに基づく「有害性の有無」である。例えば、華やかな容姿の人や男女片方をターゲットにした広告が自動的に禁止されるわけではない。ただし、子ども向けに「女の子らしさ」「男の子らしさ」のステレオタイプを並べて描くことは悪影響を与えるとして禁止対象になりうるという。
藤田氏からは、自身のBPOにおける経験に基づき、CAPが実際にどのように機能しているのか、コピーアドバイスチームに寄せられる相談件数などの具体的な質問が出された。Leung氏からは、年間約3000~4000件の質問が寄せられ、ジェンダーに関するものは最近3年間で28件であるとの回答があった。小西氏からは、日本における広告のジェンダー炎上事例などを踏まえ表現の自由とのバランスに関する質問があり、Leung氏からは消費者の考えを多数聞いた上で定量分析を行い、学術的な助言を得ながらルール策定をしているとの回答があった。
その後、事前申し込み時とウェビナー参加者から寄せられた質問に基づく質疑応答を行った。現時点では広告のジェンダー表象への規制がない日本において、どのように建設的な議論を始めることができるか、という質問について、Leung氏は英国ではマルチ・ステークホルダーで議論を深めていったという経験の共有があった。いかなる広告表現が有害とみなせるのか研究者がエビデンスを示し、何を規制すべきか市民社会からの意見を聞き、実際に広告を制作する人の話も聞くことで英国社会全体の合意形成をしてきたという。本研究会を契機に日本国内の議論を深めていく可能性を感じた。
本研究会はzoomウェビナー使用し、日本語・英語の同時通訳を利用した。参加者アンケート(回答29名:参加者の42%)によれば、51.7%はメディア学会非会員だった。また、同時通訳がいなかった場合に本研究会に参加したという回答は37.9%であった。